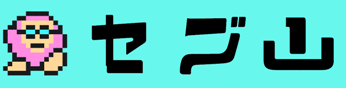すごい速さで離れていく地面を眺めながら、この滞在での思い出に回想を巡らせていた。
「次はいつ会えるだろうか…」
小さな気泡が生まれては消えてゆく黒い飲み物をじっと見ながら、ひとりそうつぶやいた。
隣の席の知らない人が、ちらりとこちらを見たような気がしたが、そんなことどうでもよかった。
鎧のように疲れを纏い、私の身体は“眠り”を最優先にしていたからだ。
早く帰ってベッドに飛び込んでしまいたい。
揺れに身を預けているうちに少しずつ意識が薄れてきた。
そうだ、帰らないと。
あの家で、今日も私は独りぼっちなのだ。
◆◆◆
「ただいま……」
玄関ドアを開けると同時に、誰もいない部屋に向かって挨拶をする。
電気をつける気にすらならず、そのまま靴を脱いで部屋に上がる。
カバンを投げ捨てて、スーツのままソファに倒れ込んだ。
「つかれた……」
思わず漏れた声には、自分でも驚くほど覇気がなかった。
こんな弱々しい声が出るなんて初めて知った。
言語が通じなくても、私の声を聞いただけで、その言葉の意味までわかってしまうくらいに。
お腹が空いた。シャワーを浴びたい。
洗濯物を取り込まないといけないし、溜まったゴミを捨てないと…… だけど今はとにかく眠ってしまいたい。
何もかも忘れてしまいたい。
明日になったらきっと全部元通りだから……。
そんなことを考えている間に、瞼が落ちてくる。
ああ、ダメだ。このままじゃ寝てしまう。
せめて着替えだけでもしておかなければ……。
頭ではそう考えているはずなのに、いつの間にか私は意識を失っていた。
◆◆◆
どれくらい時間が経っただろうか。
突然響いたインターホンの音で目が覚めた。
ピンポーン、
ピンポンピンポピーンポーン!
しつこいくらい繰り返される音に驚いて飛び起きる。
一体誰だろう?
セールスとかなら居留守を決め込めばいいけれど、もしも知り合いだったりしたら面倒だ。
恐る恐るインターホンの画面を確認してみると、そこには見慣れない人影が映し出されていた。
全身真っ黒な服に身を包み、顔はよく見えないが背は高い。チラッと見切れた髪の色は暗い赤茶色といったところか。
微妙に画角の外側に立っているので、男なのか女なのかよくわからない。
不審者かもしれないと思いつつも、無視するわけにもいかないのでドアの鍵を開けた。
もちろんチェーンロックをかけたままで。
扉をゆっくり開くと、相手はいきなり大声で話しかけてきた。
「やっほ!久しぶり!」
聞き覚えのある女性の声。
よく知っているその顔を見て、私は慌てて扉を開こうとして、チェーンが勢いよく突っ張った。
急いで扉を閉じて、ロックを外し、今度は大きく開いた。
「な、なんでここにいるんだよ!?」
そこに立っていたのは紛れもなく私の元妻だった。
最後に会った時よりもいくらか痩せているが、間違いない。
「えへへ、来ちゃった」
そう言って笑う彼女に懐かしさを感じながらも、混乱している寝起きの頭を必死に落ち着かせる。
「来るって連絡よこしたか?」
「ううん、サプライズ訪問だよ。びっくりした?」
「びっくりも何も、急すぎるって……」
「だってずっと会いたかったんだもん。仕方がないじゃん」
全く悪びれた様子のない彼女の態度に呆れつつ、中に入れることにした。
「とりあえず上がってくれ」
私がそういうと、彼女の顔はパーッと明るくなり、ニカッと笑った。
◆◆◆
「わあ〜、綺麗なお家〜」
まるで新築の家に初めて足を踏み入れた子供みたいにはしゃいでいる。
そんな彼女を少し離れて観察しながら私は言った。
「どうやってここに来たんだ?まさか、またタクシーに乗ってきたんじゃないだろうな」
「大丈夫、ちゃんと電車使ったから」
得意げに胸を張る彼女を見ていると、なんだか取り乱している自分が馬鹿らしくなってきた。
ため息なのか深呼吸なのか、自分でもわからない深い息を吐いて、彼女に尋ねる。
「それで、何しに来たんだ?」
「…………」
彼女は急に深刻そうな顔になった。
そういえば、同じようなことが前にもあったような気がする。
あれはまだ俺たちが結婚する前に……
「……離婚届けを渡しに来たの」
そう言うなりカバンの中から紙を取り出した。実物を見るのは初めてだが、それは紛うことなき離婚届であった。
「……わざわざそのためにここまで来たのか?」
「当たり前じゃない。この街は思い出の場所だし、それに……」
そう言いながら、彼女は一枚の写真を見せた。
そこには赤ん坊を抱いた女性の姿があった。
「この子にとってお母さんは私しかいないものね」
写真の中の女性は幸せそうに笑っていた。
それを見た瞬間、私の中にドロドロとしたどす黒い炎が燃え上がり、目の前の女のことをひどく憎く思った。
「ふざけんな!!」
◆◆◆
ピンポーン、
ピンポンピンポピーンポーン!
「…!?」
しつこいくらい繰り返される音に驚いて飛び起きる。
夢の中では、ありえないことが次々と起こるのに、どうして「これは夢だ」と気付けないのだろうか。
それにしても、生暖かく、リアルで、不穏な夢だった。
ピンポンピーンポーン!
時計を見ると午前2時半。まだ夜中のようだ。
““ピンポーン””
今度は先程より控えめだが、はっきりと意志を持って押された音が聞こえた。
誰かが訪ねてきているらしい。
こんな時間に一体誰が?
足音を立てないようにゆっくり起き上がり、恐る恐るインターフォンをのぞき込む。
暗く小さな画面越しではよくわからない。
意を決して“通話ボタン”を押し、話しかける。
「どちら様ですか?」
「…………」
「あの、どちら様ですか?」
「私ですけど……」
私……?
私って誰だ……? その言葉を聞いて、夢の中で見たあの女性を思い浮かべたが、どうも声質が違う。
ガチャリと玄関を開ける音がした。
「…え?」
しまった、疲れ果てていて鍵をかけるのを忘れたか?
それとも……、
急いでリビングのドアから顔を出して、玄関を確認する。
するとそこには、全身黒い服を着た、長い髪の女が立っていた。うなだれているので、顔はよく見えない。
けれど、一目見てわかった。あいつだ、間違いない。
私が殺したはずの女がなぜ今になって……。
「どうしたでござるか?」
リビングと玄関を結ぶ廊下の天井から、ひょっこりと忍者の忍助(にんすけ)が顔を出した。
俺が寝ている間に来ていたのか。
「忍助、逃げろ!」
叫ぶと同時に俺は走り出した。背後からは女の叫び声のようなものが聞こえる。
「ちょ、ちょっと、主殿(ぬしどの)!?」
「いいから!忍助!煙幕だ!」
「まったく、忍者使いが荒いでござるなぁ~~…」
ぼわわわぁぁ~~~~ん
◆◆◆
「ゲホッ、ゴホ……おい、もういいぞ、忍助」
咳き込みながらもなんとか無事に逃げ出すことができた。ふぅ……。
「なんなのでござるか、今のは?」
「わからない。ただのイタズラか、それとも本当に幽霊なのか……」
一瞬の沈黙の後、忍助が心配そうに口を開いた。
「これからどうするでござるか?」
また一瞬の沈黙があった後、今度は俺が答えた。
「とりあえず、シチューうどんでも食べに行くか」
パーッと忍助の顔が明るくなり、ニカッと笑った。
こいつのこういうところが大好きだ。

シチューうどん/550円(大阪・あづま食堂)